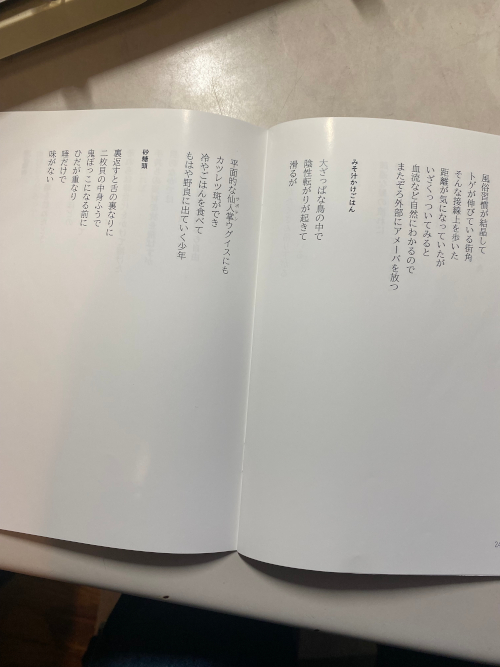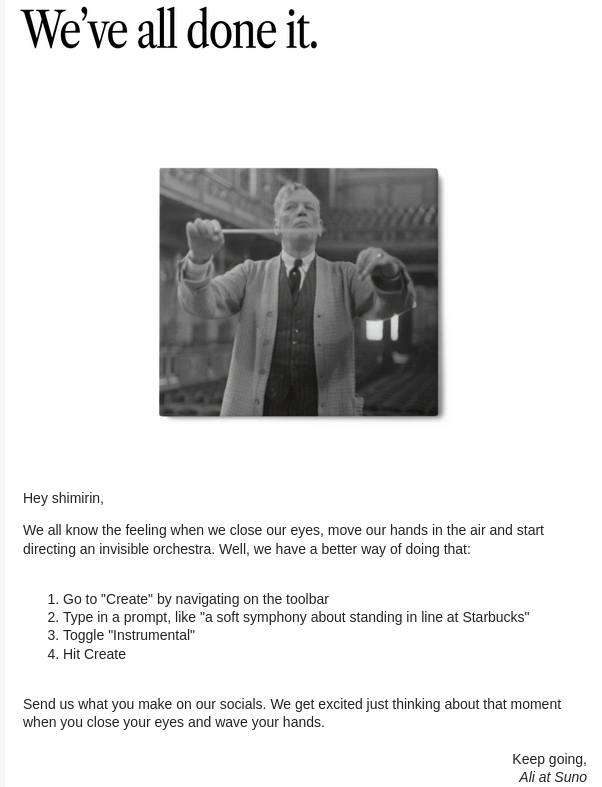今日は新パソコンのパーツを開封して、ひととおり眺めた。
1つを除いて届いているので、30日に仕上げようと思っている。
テプラで作製日付を記したシールも作っておいた。作製年月日で、劣化の程度が推し量れるのでこのごろ新しいのを作ったときケースに貼っている。
黄バラが満開になった。今年はモッコウバラと開花が重なっている。

YouTubeの朗読ファイルは、スマホで見ている人が圧倒的に多い。
ぼくは大画面で見ているが、この傾向はずっと続いていくのだろうか。
朗読ファイルはどこまでblogにリンクしたのか忘れてしまって、抜けているかもしれない。下は今日YouTubeにアップロードしたもの。